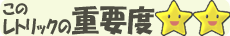サイト全部のトップ
サイト全部のトップあて字 あてじ phonetic equivalent

- 古雪の兄「くつろいでる
- 場合か」
- 古雪「お お兄ちゃん!?
- なんでいるのよ?
殺 した- ハズなのに!!」
- ピロスケ「うわっ
- その当て字は
- ダメでふよ!!
- “消”したでふッ」
- 古雪の兄「き 貴様
- 実の兄を
殺 しただと ——!?」
あて字は、「漢字」それ自体がそれぞれもっている意味と、その読みかたとなる日本語がもっている意味。この2つが、ずれているばあいをいいます。
 もともと「漢字」では表現できないモノゴトを示すことができる
もともと「漢字」では表現できないモノゴトを示すことができる
- たとえば、「足袋(たび)」というもの。これは、(たぶん)中国語としては存在しなかったはずです。けれども日本では、ごくふつうに日常の生活に存在する。そのため、「たび」ということばを表す方法を、新しくつくる必要があった。こんなときに、「あて字」が活躍します。
 漢字で書いたほうが権威がつく
漢字で書いたほうが権威がつく
- 日本では、「漢字で書くものが、正式のものだ」という考えがありました。だいたい、明治時代くらいまでは、この傾向が強かったということができます。そんなわけで「あて字」は、偉そうなイメージを出すことができます。
 外国にある地名や国名を、1文字に省略できる。
外国にある地名や国名を、1文字に省略できる。
- イギリスは、「英吉利」と書いていた。なので短くすると、「英」と表すことができる。フランスは「仏蘭西」なので、「仏」となる。まあ、そういったぐあいです。なおマメ知識として、アメリカが「亜米利加」なのに「亜」ではなくて「米」と書かれる理由。それは、アジア(亜細亜)とダブってしまうからです。
 :外来語、外国語
:外来語、外国語
 ことば遊びの面がある
ことば遊びの面がある
- たしかに「あて字」は、必要だからこそ使われることになった。それは、まちがいありません。ですが、「言葉あそび」という面も、ちゃんと備えています。「クラブ」のあて字に、「倶楽部」という漢字が使われている。この漢字からは、たんなる「発音」の一致だけではないニュアンスを感じとることができると思います。
 :ことば遊び、戯書、文字遊び、文字遊戯
:ことば遊び、戯書、文字遊び、文字遊戯
 「漢字」のもっている音のうち、「音読み」だけを借りてくる(=音借)
「漢字」のもっている音のうち、「音読み」だけを借りてくる(=音借)
- 「漢字」は、それぞれ1文字が「意味」と「発音」とを兼ねそなえています。そして、「漢字」がもっている「発音」には、「音読み」と「訓読み」とがあります。つまり、1つの「漢字」には、「意味」「音読み」「訓読み」という3つの要素があるというわけです。
で、まず「発音」のうち「音読み」だけを借りてする。つまり、「漢字」が持っているうちで「意味」と「訓読み」については無視する。これが、「あて字」をつくるパターンの1つ目です。
たとえば「素敵」という単語を見てみる。
すると、たしかに「素」を「ス」と読むことはできるし、「敵」を「テキ」と発音することもできます。そして、「ス」と「テキ」は両方とも「音読み」です。
だけれども、「素」という漢字のもっている意味と、「敵」という漢字が表すことになっている意味とは、まったく無関係です。このようなものが《「あて字」その1》となります。
なお、これは専門用語で「音借」と呼びますが、それは忘れてかまいません。
 :借字、借義、借音、音訳、音をうつす、仮借(かしゃ)、ふりがな、ルビ
:借字、借義、借音、音訳、音をうつす、仮借(かしゃ)、ふりがな、ルビ
 「漢字」のもっている音のうち、「訓読み」だけを借りてくる(=訓借)
「漢字」のもっている音のうち、「訓読み」だけを借りてくる(=訓借)
- で、次に《「あて字」その2》。
それは、「漢字」のもっている「音」のうち、「訓読み」だけを借りてくるというものです。たとえば「矢張」というつづりでもって「やはり」と読むばあいが、これに当たります。これは、「訓借」と呼ばれます。
 「漢字」のもっている意味だけを、借りてくる(=熟字訓)
「漢字」のもっている意味だけを、借りてくる(=熟字訓)
- 上に書いた2つのパターンとは反対に。「発音」は無視をして、「意味」だけを借りてきてくる。このようにして、「あて字」を作ることができます。
たとえば、「煙草」という単語。この「煙草」では、漢字のもっている「煙」と「草」という「意味」は、漢字から借りています。です「発音」のほうは、ちっとも関係ありません。「煙」という字は、「音読み」しても「訓読み」しても、「タバコ」という「発音」にたどりつくことはできません。これが、「あて字」をつくるパターンの3つ目です。
これは「熟字訓」と言われているものです。この「熟字訓」については、「あて字」とは考えないという立場もあります。
なお、「転注」という名前がついている用語があります。あくまで、個人的な考えなのですが。この「転注」というヤツは、「熟字訓」と同じ発想でのものだという気がしています。ですが、いまいち自信がありません。なので、ちゃんとした根拠なり証拠なりが見つかるまでのあいだ、保留としておきます。
 :熟字訓
:熟字訓
 外国の地名や人名は、ふつうカタカナで書く
外国の地名や人名は、ふつうカタカナで書く
- 当然といえば、それまでなのですが。
外国の地名や人名のうち、ほとんど漢字でことがないものを漢字で書ということ。それは、もはやクイズです。「古論武士」は、「コロンブス」というふうに、カタカナで書いてもらわないと困ります。
ただし例外として、中国の地名と人名だけは、「北京」でも「天津」でも漢字で書くことになっています。「毛沢東」は、カタカナで「マオツォトン」とはしないで「毛沢東」と表記します。
 :誤字
:誤字
- 引用は『プラネットガーディアン』2巻から。
主人公は、「如月小雪」。
まず。
引用の場面を見てみる前に、舞台設定を読んでみることにしましょう。ちょうど2巻の帯に簡単なストーリーが書いてあるので、書きうつしてみます。謎の生物から、凶暴な異星人と戦う力を授かった如月古雪は受験生!地球を守る使命よりも、明日のテストの方が大切で仕方がないのだが…。(以下略)とのこと。
そして重要な点は、古雪の兄がもっている性格。古雪の兄は、すこし変わった性格なおんです。これも、巻頭のプロフィールから抜き出してみます。高校生。古雪に魔女っ子らしさを強要するため、古雪がもっとも激しく嫌悪する人物。(以下略)まあ、そういったのが舞台設定となります。
そんな古雪が、意識を乗っとってくる異星人と戦う。そして、その戦いの中で異星人に寄生され、古雪は意識を侵されてしまう。結果、彼女の意識は、すっかり異星人を受け入れてしまう。
でもって、古雪の意識の中。ここでは、古雪の兄の存在が部屋ごと消滅させられてしまう。もちろん上に書いたように、兄は古雪に魔女っ子らしさを強要するため、古雪がもっとも激しく嫌悪する人物だから。
その気持ちを述べているのが、引用のシーン。つまりという表現が、「あて字」となるわけです。ウソだと思うのなら、手近なIMEで「けす」を変換してみてください。「消す」は出てくるけれども、「殺す」は出てきません。殺 した
ちょうどピロスケも、「あて字」だって言っていることだし。引用したものを、「あて字」の例としておくことにします。
 「あて字」と「添義法」との関係
「あて字」と「添義法」との関係
- 「あて字」というのに似たレトリック用語として、「添義法」というものがあります。「添義法」というレトリックも、あることばにフリガナをつけることで、なにかメッセージを伝えようとするものです。
ですが、これから説明するように。「あて字」と「添義法」とでは、ちょっと役割が違っています。
そこで、このサイトでは。
「あて字」と「添義法」というレトリック用語について、次のように割りふっておきます。
「あて字」については、それなりに使われているもの。つまり、一般にも見られるような独自性の低いもの。
反対に「添義法」については、はじめてお目にかかるようなもの。ようするに、独自性が高くて、日ごろ見かけないようなもの。
以上のように、「あて字」と「添義法」を分けておきます。
なぜ、このような割りふりをするのか。それは、「フリガナ」が必要なものなのか、それとも、なくても構わないものなのかという点。そこに、ちょっとした違いがあるからです。
もっと、具体的に言えば。
「あて字」は「一般的に使われている」ものです。なので、「フリガナ」がなくても読むことができるわけです。そのため 「あて字」は、かならずしも「フリガナ」があるとは限らないのです。もちろん「フリガナ」がついているばあいも多くあります。ですが、絶対に「フリガナ」が必要だというものではありません。
それにたいして「添義法」。これは、「はじめてお目にかかるような」もの。なので、「フリガナ」がないと絶対に読めないのです。なので、必ず「フリガナ」をつけることが求められます。したがって、「フリガナ」のない「添義法」というのは、ありえません。
ここに ひとつ。
「添義法」と「あて字」との違いを説明する。そのために作られたフレーズなのではないかと思うような、ピッタリな文があります。乙女はお姉さまに恋してるという文字がならんでいる。これには、と「フリガナ」が書いてある。つまり、乙女 はボク に恋してるおとめ は ボク に こいしてるというふうに、読まなければならない。そういうわけです。
ここで。まず、「乙女」にたいして、「おとめ」という「フリガナ」がある。これは「あて字」です。厳密に書いておけば、「 熟字訓」です。「乙女」のほうは、もしも「フリガナ」がないとしても「おとめ」と読むことができます。
熟字訓」です。「乙女」のほうは、もしも「フリガナ」がないとしても「おとめ」と読むことができます。
これにたいして。「お姉さま」という単語に、「ボク」という「フリガナ」がついている。これは「添義法」です。「お姉さま」という文字だけを見ただけでは、「ボク」と読むのはムリです。「お姉さま」ということばで「ボク」と読むことには、じゅうぶんな独自性があります。
ま、そういったわけです。
 上に書いたように、「あて字」を定義してみると
上に書いたように、「あて字」を定義してみると
- 上に書いてきた、そんな分けかたをすると。結局「あて字」というのは、かなり決まりきった表現に限られます。たとえば、「五月雨」を「さみだれ」と読んだり、「出鱈目」を「でたらめ」と読むといったようなものを「あて字」と読むことになります。
なので。この「あて字」については、「レトリック」というかんじがしません。どちらかというと、「国語学」に近いといえます。

- あて字・当て字・宛て字・宛字
 『国語学大辞典』(国語学会[編]/東京堂出版)
『国語学大辞典』(国語学会[編]/東京堂出版)
- この、図体のデカい辞典を見れば。1から10まで、シッカリした説明が書いてあります。まあ、こんな本を見るために図書館まで足を向けるようなヒトは少ないとは思うけれど。
 『新版文章表現辞典』(神鳥武彦・村松貞夫[共編]/東京堂出版)
『新版文章表現辞典』(神鳥武彦・村松貞夫[共編]/東京堂出版)
- こちらは。「辞典」というわりには、平均的な説明ばかりが書いてあるわけではない。そこが、大きな特徴です。
 「処女はお姉さまに恋してる」の「処女」を、「おとめ」と読むことについて
「処女はお姉さまに恋してる」の「処女」を、「おとめ」と読むことについて
- 「乙女はお姉さまに恋してる」というタイトルは、アニメのためにつけられたものです。そして、このアニメには、原作のゲームソフトがあります。そのタイトルは、「処女はお姉さまに恋してる」というものです。ようするに、「乙女」ではなく「処女」という漢字が使われているのです。読みかたは、同じ、「おとめ は ボク に こいしてる」というものです。つまり、「処女」にたいして「おとめ」という「フリガナ」があるわけです。
ここで、ちょっと考える。「処女」にたいして、「おとめ」という「フリガナ」がある。これは、「あて字」だろうか、それとも「添義法」となるのだろうか、と。
たぶん、このあたりが「あて字」と「添義法」とのボーダーラインなんだろうな、という気がします。
ためしにgoogleで検索したときのヒット数は、つぎのとおりでした。(2008年7月現在)「処女」+「おとめ」→261,000件なお。
参考:
「殺る」+「やる」→163,000件 (このサイトで例にしたもの)
「麦酒」+「ビール」→391,000件 (典型的な「あて字」の1つ)
「処女はお姉さまに恋してる」というソフトは、かなりヒット商品だったようなので。そのあたりが、検索ヒット数に大きな影響を与えていることが考えられます。私(サイト作成者)は、アニメから入ったので。そのへんは、くわしくありません。