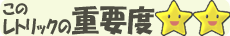サイト全部のトップ
サイト全部のトップ破格くびき はかくくびき syllepsis,zeugma
![『“文学少女”と死にたがりの道化(ピエロ)』1巻53ページ(野村美月[原作]・高坂りと[作画]/スクウェア・エニックス ガンガンコミックス JOKER)](http://www.fukirhetoric.com/image/jpg/bungakushojotoshi1-53.jpg)
- 天野先輩「へんに技巧に走った
- 文章より
- 普段書かない人が
- 一生懸命書いた
- 真実の言葉の方が」
- 「胸にもおなかにも
- 染みるものよ」
破格くびきは、1つの単語が2つ以上のことばに結びついているけれども、その片方には何らかの誤りがあるというものです。この「何らか誤り」というもの。これは日本語では、意味が沿わないためのものが一般的です。なのでとりあえず、「意味が沿わないこと」によって生じた「破格くびき」について書いていくことにします。
 矛盾した言葉づかいによって、おもしろさを引き出す
矛盾した言葉づかいによって、おもしろさを引き出す
- 「破格くびき」では一見すると、1つの語が2つの表現に結びついているように思えます。ですが実際には、結びついていると思われるどちらかの単語に関しては、理屈に合わない間違った結びつきとなっています。この間違った結びつきを意識しておこなうことで、おもしろいフレーズをつくるなど、なにかしらの効果をみちびきだすことができます。
 :矛盾、ずれる、食い違う、齟齬、筋違い、背反、撞着、共通因子、つなぎ合わせる、カッコでくくる、結びつける、束ねる、くびき、ズレたむすびつき、接続、つなぐ、つなげる
:矛盾、ずれる、食い違う、齟齬、筋違い、背反、撞着、共通因子、つなぎ合わせる、カッコでくくる、結びつける、束ねる、くびき、ズレたむすびつき、接続、つなぐ、つなげる
 「兼用法」に近い効果をえることができる
「兼用法」に近い効果をえることができる
- 「破格くびき」を使うことによって、「 兼用法」と同じような効果をえることができるといえます。これは、「破格くびき」は、おなじ「くびき語法」のグループに含まれる「 兼用法」と、厳密には区別することはできないということも影響しています。
 :兼用法
:兼用法
 片方にしか、意味が当てはまっていない
片方にしか、意味が当てはまっていない
- くびきのように結びつけられた、それぞれのことばとの関連を見てみる。すると、その片方にしか意味が当てはまらない。言いかたをかえれば、もう一方のほうにたいしては、意味が適合していない。そのような言いまわしを意図的にわざとすることによって、「破格くびき」をつくりだすことができます。
 :(意味が/意味論的に/意味の結びつきが)沿わない、はまらない、当てはまらない、不適合、不相当、そぐわない、符合しない、合致しない、適合しない、片方にしか関連しない、片方にしかかかわらない、片方にしか関係しない、片方にしか結びつかない、片方にしかつながらない
:(意味が/意味論的に/意味の結びつきが)沿わない、はまらない、当てはまらない、不適合、不相当、そぐわない、符合しない、合致しない、適合しない、片方にしか関連しない、片方にしかかかわらない、片方にしか関係しない、片方にしか結びつかない、片方にしかつながらない
 そのため、何らかの語句を補うと分かりやすい
そのため、何らかの語句を補うと分かりやすい
- 意味が当てはまっていないということは。ちゃんと当てはまるように、ふさわしい意味の単語を補ってみると文が受けいれやすくなるということでもあります。
 :(語句を)補う、埋める、埋め合わせる、足す、補充、補足
:(語句を)補う、埋める、埋め合わせる、足す、補充、補足
 「単なる間違い」だと受けとられることがある
「単なる間違い」だと受けとられることがある
- 「破格くびき」は、その一方にしか意味があっていないものです。つまり、他方にたいしては意味が合っていないものです。意味が合っていないということは、レトリックの一種であるというよりも「単なる間違い」だと受けとられかねない。そういった危険が高いのが、「破格くびき」の難点だといえます。
 :(意味が/意味論的に/意味の結びつきが)誤用すれすれ、誤りに近い、間違いに近い、手違いに近い、言い損ないすれすれ、書き損ないすれすれ
:(意味が/意味論的に/意味の結びつきが)誤用すれすれ、誤りに近い、間違いに近い、手違いに近い、言い損ないすれすれ、書き損ないすれすれ
- 引用は、『”文学少女”と死にたがりの道化(ピエロ)』1巻からです。
主人公は、井上心葉(このは)。
1年前のこと。
心葉(このは)は、文芸部に在籍している天野先輩が「本を(1ページずつ切り取って)食べる」のを目撃する。そして、それを目撃されてしまった天野先輩は、心葉(このは)を文芸部に入部させられる。心葉(このは)を監視するために。
さて、天野先輩は「本を(1ページずつ切り取って)食べる」わけですが。その味は、本の好き嫌いだとか、上手下手によって決まるようです。
んなところで、引用のシーン。天野先輩によると本は、胸にもおなかにも染みるものよとのこと。そして、これが「破格くびき」にあたります。
文章をそのまま原則どおりの「くびき語法」にあてはめれば、次の図のようになります。
①のほうは「胸に—染みる」なので、なにも問題はありません。ですが、②のほうは「おなかに—染みる」となっていて、これには違和感があるはずです。①胸に ┐
├染みる
┘②おなかに
どのくらい、「胸に—染みる」「おなかに—染みる」という日本語が使われているのかを、googleで調べてみます。すると、- 「文章が胸にしみる」…約7,760件
- 「文章がお腹にしみる」…0件
つまり、「文章が胸にしみる」は、意味として通じることができるものです。だけれども、「文章がお腹にしみる」のほうは、意味としては、ふつう通じるものではありません。
というわけで、「(意味論的な)破格くびき」といえるわけです。 「破格くびき」の例を、もうひとつ
「破格くびき」の例を、もうひとつ
- もうひとつ、小説から例を。
「破格くびき」が使われているのは、たとえば、といったもの。これが、典型的な「破格くびき」です。- 「私は最近はじめてこの手でこの目で触れたのだ」
- ——(吉本ばなな『キッチン』)
これをよく見てみると、
となる。①この手で ┐
├触れる
┘②この目で ここで、「①この手で—触れる」は、ごくふつうの文です。しかしながら、「②この目で—触れる」というのは、かなりフシギな文になっています。
ほかの言いかたをすれば、のです。- 「くびき」をもとに戻すと、
- 「この手で触れたのだ」
- +「この目で触れたのだ」となる。
- 「この目で触れる」という表現は
- 合っていない。
この点が「破格くびき」の大きなポイントです。
 「くびき語法」のグループに含まれる、ほかのレトリック用語との関係
「くびき語法」のグループに含まれる、ほかのレトリック用語との関係
 これから書いていく「関係」を図で表すと
これから書いていく「関係」を図で表すと
- 次から書いていく「くびき語法」に含まれるレトリック。これをカンタンな図で表すと、次のようになります。
くわしくは、下にある文法的に
正しいか意味的に
正しいか名称 くびき語法
(広義の)○ ○ くびき語法
(狭義の)△(本来の意味と比喩的意味) 兼用法(異義兼用) △(具体的な意味と抽象的意味) 異質連立 × 意味論的破格くびき 破格くびき × ○ 統語論的破格くびき  以降をご覧ください。
以降をご覧ください。
なおこのサイトでは、『レトリック事典』をもとにして定義づけをしています。
 単純な「くびき語法」との関係
単純な「くびき語法」との関係
- 見た目だけの、ことばの操作を見れば。「破格くびき」のやっていることは、単純な「 くびき語法」のものと同じです。共通することになることばを、くくり出す。これについては、くわしくは「 くびき語法」をご覧ください。
 「兼用法」との違い——完全に意味が間違いになっている
「兼用法」との違い——完全に意味が間違いになっている
- つぎに、「破格くびき」と「
兼用法」との違い。ここでポイントとなるのは、というところです。
- 結びついているどちらの単語にも、
- 意味として成りたっているかどうかが
くくり出した「動詞」を元にもどしてみる。すると、そのことばが片方ではたらいている意味と、もう一方ではたらいている意味とが違う。そういったものが、「 兼用法」にあたります。
いいかえれば。1つしかないことばが、くびきのように2つ以上のことばへと結びついている。その2つ以上のことば、それぞれとの関係で、くびきとなっている語の意味が別になっているというものです。
とくに。片方では「本来の意味」となっているが、もう一方では「比喩の意味」となっていることが多くあります。
「 兼用法」の使われたものとしては。たとえば、といったものが、あげられます。- 「思惑だの褌(ふんどし)なんてえものは、
- えてして外れやすい」
- ——(五代目古今亭志ん生『びんぼう自慢』)
というのは。これをよく見てみると、もとに戻すと、からです。- 「褌(ふんどし)が外れる」のほうは
- 「本来の意味」ということができる。
- だけども、「思惑が外れる」のほうは
- 「比喩の意味」といえる。
このように。
あくまで「 兼用法」は、いちおう意味として成りたっているのです。ただし、結びついているそれぞれのことばとの関係で見てみると、食い違いがある。
これにたいして。
「破格くびき」のほうについては。完全に意味として、誤りがある。そこに、大きな差があります。
くわしくは、「 兼用法」のページをご覧ください。
まあ、もっとも。
「合っている」のか、それとも「合っていないのか」ということ。この判断は、じつはかなり難しいものです。とくに、比喩として使われている「兼用法」ようなばあい。それがどこまで、ふつう許された使いかたをなされているのかということは、いちがいに決められないこともあります。

- 破格くびき

- 不一致的軛語法
 『レトリック事典』(佐藤信夫[企画・構成]、佐々木健一[監修]、佐藤信夫・佐々木健一・松尾大[執筆]/大修館書店)
『レトリック事典』(佐藤信夫[企画・構成]、佐々木健一[監修]、佐藤信夫・佐々木健一・松尾大[執筆]/大修館書店)
- 「破格くびき」について、かなりくわしい説明が書いてあります。「1-8-1-2-4《破格くびき》」という項目が、その説明となっています。
 『文学修辞学—文学作品のレトリック分析—』(H.ラウスベルク[著]、萬澤正美[訳]/東京都立大学出版会)
『文学修辞学—文学作品のレトリック分析—』(H.ラウスベルク[著]、萬澤正美[訳]/東京都立大学出版会)
- どうしても、「統語論的に錯綜した破格くびき」(下の【余談】に説明してある)について良く知りたいという方は。この本を見るのが、オススメです。例文はラテン語、フランス語、古代ギリシア語とさまざま。まあ私(サイト作成者)が、ラテン語もフランス語も古代ギリシア語もまったく読めないので、ちゃんと理解はできていないのですが。
 文法の面での「破格くびき」について
文法の面での「破格くびき」について
- さて、ここまで書いてきた「破格くびき」の説明。その中では、「意味の面」で誤りがあるものを扱ってきました。つまり、くくられている片方のことばにたいしては「正しく」かかっている。けれども、もう一方のことばにたいしては「意味が誤って」かかっている。このようなものについての説明を、ここまで書いてきました。
ですが。
じつは「破格くびき」には、もう1つのタイプがあります。それは、「文法の面」での誤りがあるものです。そしてとくに、「統辞論的な面」での間違いがあるものを指すことが一般的です。
そういったわけで。
これから先は、「統辞論的な面」での「破格くびき」について書いていくことにします。
ことばの使いかたとして。
これまでずっと書いてきたものは、「意味論的に錯綜した破格くびき」。それにたいして、これから書いていくことになるのは「統語論的に錯綜した破格くびき」。とまあ、そういったふうに分けて書いていくことにします(なんだか長いネーミングで、申しわけありません)。
 では、「統語論的に錯綜した破格くびき」とはなにか
では、「統語論的に錯綜した破格くびき」とはなにか
- その「統語論的に錯綜した破格くびき」とは、いったいなにか。英語の例になってしまうのですが、あげてみます。
『現代言語学辞典』(田中春美[編集代表]/成美堂)に書いてある、The apple was eaten and the bananas neglected.(りんご《単数》は食べられ,バナナ《複数》は無視された)というもの。これは、「統語論的に錯綜した破格くびき」です。日本語への訳文にも書いてあるとおり、りんごは《単数》だから、wasを使うことができる。けれども、バナナは《複数》だから、wasを使うことはできない。よって、文法としては正しくない。
たしかにこんなのは、話しことばでは十分に出てくる可能性がある。けれども、あえてこのようなことを意図的におこなって、なにか効果をえようとしているものがあるとすれば。それは、「統語論的に錯綜した破格くびき」です。
 けれども、「統語論的に錯綜した破格くびき」は日本語には少ない
けれども、「統語論的に錯綜した破格くびき」は日本語には少ない
- とまあ、「統語論的に錯綜した破格くびき」について書いてきたのですが。じつは、この「統語論的に錯綜した破格くびき」は日本語では、めったに見つけることができません。
その理由は。
日本語では、統語のルールがとても甘いだからです。統語のルールが、ゆるやか。だから、それを違反することも、めったにない。そういったわけで、日本語での例を探すのは、カンタンではありません。
私(サイト作成者)は、これまでのところ。日本語の文章で、「統語論的に錯綜した破格くびき」になっているものを、見たことがありません。
だいたいどんな本を見ても。「統語論的に錯綜した破格くびき」の例としてあがっているのは、英語とかフランス語です。こういった言語は、文法ルールがキビシい。あれこれ文法にルールがあるということは、そのルールを違反しやすい。そのため、「統語論的に錯綜した破格くびき」になりやすいということです。