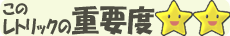サイト全部のトップ
サイト全部のトップ挙例法 きょれいほう examples

- マリエ「——これは 挑戦だわ[
- 上等じゃない
- 山野花!!
- カレーに 福神漬がつくように
- 恋にはライバルが
- つきものなのよ!!
- 行くわよ!!
- アシスタンツ!!」
- アシスタンツ「はい!!!」
挙例法は、その名前のとおり、「例を挙げる」というレトリックです。つまり、何か特殊な例をあげて、そこから結論を引きだそうとするものです。
 理解を助けたり、相手によく理解させることができる——「説明」
理解を助けたり、相手によく理解させることができる——「説明」
- 抽象的で概念的な内容のばあい、そのことに対する理解をうながすことで、説明に広がりが生まれます。また感覚的にも理解しやすくなり、実感が持てるようになります。
 :具体的、具体、具体化、具象、実感、理解、分かる、解する、解せる
:具体的、具体、具体化、具象、実感、理解、分かる、解する、解せる
 相手を説得し、納得させることができる——「説得」
相手を説得し、納得させることができる——「説得」
- 「挙例法」は、ただ「説明」のために使われるのではありません。多かれ少なかれ、受け手(聞き手・読み手)を説得することで、納得してもらうという面もあります。
 :説得、説く、納得、了解、首肯、合点、得心、感じとる、感受
:説得、説く、納得、了解、首肯、合点、得心、感じとる、感受
 相手の主張に異を唱える——「反論」
相手の主張に異を唱える——「反論」
- 「説明」や「納得」させるチカラのある「挙例法」は、相手の主張に異を唱えるときにも役に立ちます。
 :反論、言いあう、言いあい、言い争う、口げんか、いさかい、口論、反駁、論駁、弁駁、抗論、抗議、もの申す
:反論、言いあう、言いあい、言い争う、口げんか、いさかい、口論、反駁、論駁、弁駁、抗論、抗議、もの申す
 例をあげるときには、似たものを例として取りあげる
例をあげるときには、似たものを例として取りあげる
- ふつう例をあげるときは、似たものを例として挙げます。つまり、例をあげたいと思っているシーンに似たことがらを選ぶことになります。こちらがスタンダードです。
 :似る、似合う、類する、類似、類同、近似
:似る、似合う、類する、類似、類同、近似
 ふつうは似ていないと考えるものを、例としてあつかう
ふつうは似ていないと考えるものを、例としてあつかう
- あまり似ていないものを、例として取りあげる。そのことで、一見すると意外ではあるけれども、よく考えてみれば納得のいく例だと思うことができるようになります。
 :意外、思いがけない、思いもよらない、思いの外、図らずも、偶然、意想外、心外、存外
:意外、思いがけない、思いもよらない、思いの外、図らずも、偶然、意想外、心外、存外
 「似たものどうし」であるといえるか?
「似たものどうし」であるといえるか?
- 例としてあげることになるシーン(=引用元)と、例を取ることになるシーン(=引用先)。この2つが全く似ていないものであるならば、その挙例法は失敗だといえます。
 「似たものどうし」でも、そのシーンでは例として不適切ではないか?
「似たものどうし」でも、そのシーンでは例として不適切ではないか?
- 「引用元」と「引用先」とが似ていたとしても、その例が、引用先でのシーンに当てはめるのが、そぐわないこともあります。そのようなばあいにも、「挙例法」は避けるべきです。
 そもそも、引用元が知られているか?
そもそも、引用元が知られているか?
- 例としてあげることになるシーン(=引用元)。このシーンを、受け手(聞き手・読み手)のほうが知っているかどうかは、非常に大切です。知らないものを例として出されても、なにも効果を生みません。
- 引用は『きゃらめるダイアリー』。
主人公は、山野花。[
彼女は、太郎という男の子をめぐって、マリエと三角関係。この三角関係になっている今の状態を、マリエはカレーに福神漬がつくようにという例を挙げて言っています。
「挙例法」は、難しいことを理解しやすくするために例を挙げる、ということのほうが多くあります。しかし今回は、「恋のライバル」を「カレーの福神漬」にたとえる、というところに意外性を感じたので、これを引用してみました。
ちなみに、「行くわよ!!アシスタンツ!!」というところで出てきた「アシスタンツ」というのは、マンガを書く人をサポートする「アシスタント(の複数形)」です。『きゃらめるダイアリー』では、主人公の花も、引用部分で登場したマリエも、漫画を描いている中学生だという設定になっています。
「はい!!!」
 実話ではないところを、例にする
実話ではないところを、例にする
- 例としてあげることになるシーン(=引用元)は、必ずしも現実の話だとは限りません。寓話であるとかフィクションの物語であっても構いません。
例を取ることになるシーン(=引用先)に、例としてあげることになるシーン(=引用元)がマッチしていれば、「挙例法」が成りたちます。

- 挙例法・挙例

- 例証

- 範例

- 例話・例話法・類似法・例説
 『日本語修辞辞典』(野内良三/国書刊行会)
『日本語修辞辞典』(野内良三/国書刊行会)
- かなりくわしく書いてあります。「挙例法」がもつ3つの役目などは、ここに書かれていることを参考にしています。同じ者の『レトリック入門—修辞と論証—』(野内良三/世界思想社)などにも掲載があります。