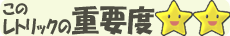サイト全部のトップ
サイト全部のトップ挿入句 そうにゅうく parembole

- 京介「何で俺の周りって
- 俺様(もしくは女王様)で
- わがままで厄介な人が
- 多いんだろう…」
- 圭(何で この人
- こんなに
- 悩むコト
- 多いのかな——)
挿入句は、文の流れを中断させない程度に、ことばを割りこませるレトリックです。
 「ことば遊び」に使われる
「ことば遊び」に使われる
- 同じ音をワザと連続させることで、「ことば遊び」に使われることが多くあります。
 :ことば遊び、言語遊戯、知的遊戯
:ことば遊び、言語遊戯、知的遊戯
 文を断ちきらない程度の長さの文(句)を組み入れる
文を断ちきらない程度の長さの文(句)を組み入れる
- 文の途中で、そのメインの文脈を断ち切らないようなことばを入れるのが「挿入句」です。言いかえれば、ことばを割り込ませるけれども、それは本文を流れをいったん中断させるほど長くはないもの、ともいえます。
 :句、組み入れ、加える、加わる、つけ加える、付け加わる、組みこむ
:句、組み入れ、加える、加わる、つけ加える、付け加わる、組みこむ
 ——ダッシュなどを使って、独立した「挿入句」をつくる
——ダッシュなどを使って、独立した「挿入句」をつくる
- ——ダッシュや( )を使うことで、「挿入句」を独立させることが必要です。これは、もしも「挿入句」がなかったとしても、完全な文としていなければならないからです。
 どこからどこまでが「挿入句」なのかを、ハッキリさせる必要がある
どこからどこまでが「挿入句」なのかを、ハッキリさせる必要がある
- 「挿入句」を使っていると、その「挿入句」から別の文が発展するということがあります。このことが、「挿入句」を使うときに注意しなければならないことです。
- 例文は『ひつじの涙』2巻から。
主人公は、「蓮見圭」。入学したての高校1年生。
——なのですが。
引用した部分は、「神崎京介」という、「圭」のクラスメイトのモノローグ。
というわけで、この『ひつじの涙』という作品の“もうひとりの主人公”にあたる、「神崎京介」。彼の視点から、ストーリーを見ていきましょう。
まず冒頭で。
「神崎京介」は困っている。なにせ、「蓮見圭」という女の子が、住んでいるマンションに入りたがっているから。
しかし、困るのである。「京介」のマンションは、姉の「おさがり」として住んでいる。そんなわけで、「京介」は、“乙女チック”な部屋に住んでいるのである。こんなことをクラスメイトに知られたら、たいへんだ。
それに、副担任の「天馬彩人」。この人、「圭」のイトコらしい。なので、「圭」が「京介」のマンションに入ることに、賛成しているようす。この人も、「京介」にとっては危険な人。
さらに、「蓮見理人」。彼も「圭」のイトコらしい。でも、「天馬彩人」とそっくりの顔立ち。で、これまた「天馬彩人」と同じく、危険な人。
とまあ、「京介」が周りを見わたせば、厄介者ぞろい。それを悩んでいるのが、引用のシーン。というモノローグの中にある、- 何で俺の周りって
- 俺様(もしくは女王様)で[[li]わがままで厄介な人が
- 多いんだろう…
ということば。これって、メインの文章を中断させてはいません。たしかに、補足として、文のなかに入りこんでいます。ですが、決して文を中断させるものではありません。このようなものが、「挿入句」です。- (もしくは女王様)
 「挿入句」のグループ
「挿入句」のグループ
- 「挿入句」の系列には、次のようなレトリックがあります。
- 挿入句:挿入する部分が短くて、もとの文を中断させずに補足する程度に限られるレトリック
- 挿入法:文の流れをいったん中断して、ある程度の長さの言葉を割り込ませるレトリック
- 挿入節:文が中断され、かなりの長さで話が横にそれるレトリック
- 脱線法:大がかりな挿入法で、話の本筋とは関係ない話が長い間、展開するレトリック
 「挿入句」と「愛称語」「換喩」との関係
「挿入句」と「愛称語」「換喩」との関係
- この「挿入句」は、文の流れの途中で、ことばを割りこませるレトリックです。つまり、ある1つの文があるなかで、とつぜん寄り道をするような「句」が入る。そして、すぐにもとの本文にもどる。それが、「挿入句」です。
なのですが、この「挿入句」を使うときには、ちょっと注意点があります。それは、「どこからどこまでが寄り道なのかということを、ハッキリさせる必要がある」ということです。
どういうことかというと。
ふつう「挿入句」で割りこむことになる「句」というのは、短いものです。そのために文の流れが、「本題」→「寄り道」→「本題」、という感じでクルクルと変わることになるのです。
これは、文を読む(または聞く)側からすると、かなりの負担になります。その文で話題にしていることが、「本題」から「寄り道」に入ったかと思えば、すぐに「本題」に戻る。こんなふうに、文のメインとなっているはずの話題が、あっちへいったり、こっちへいったり、といったことになるわけです。このことは、読み手(聞き手)のアタマを混乱させかねません。
こういったことを避けるためには。
このページで引用した例文のように、( )でくくる、といった方法があります。( )で囲まれたところは、「寄り道」だということがすぐに分かります。ですので、フラフラした文にはなりません。
もちろん。
上に書いたような( )記号だけではなく、「 」だとか〈 〉だとかで囲い込んだばあいでも、同じように混乱を避けることができます。また、そのようなカッコを使わずに、——というダッシュ記号で挟みこんでもOKです。
もう1つの方法として。
かなり難しいテクニックになりますが、「挿入句の終わりを、句点(。)で区切る」、というパターンが考えられます。ほんとうのところは、「挿入句」よりも、むしろ「寄り道」が長い「挿入法」だとか「挿入節」のほうが、使いやすいテクニックです。けれども文の流れによっては、「挿入句の終わりを、句点(。)で区切る」、といったこの方法を利用することもできます。
 『レトリック事典』での、「挿入句」の説明
『レトリック事典』での、「挿入句」の説明
- 『レトリック事典』は、「挿入法」を細かく分けることには否定的です。ようするに、確かに伝統的なレトリックでは「
挿入法」と「挿入句」とを区別していた。けれども、これを下位の種類に分類することが有意義かどうかは別である、と。
けれども、このサイトでは伝統的レトリックにしたがっておきます。つまり、いちおう「 挿入法」と「挿入句」の区別をつくっておくことにします。
なお、念のために書いておくと。
『レトリック事典』は、「挿入法(parenthesis)」のことを「(自立)挿入語句」と呼んでいて、「挿入句(parembole)」のことを「(依存)挿入語句」と呼んでいます。
 『日本語レトリックの体系』での、「挿入句」の説明
『日本語レトリックの体系』での、「挿入句」の説明
- 『日本語レトリックの体系』によると、「折挿法」というレトリックがあります。この「折挿法」は、「文の途中で他の文章をはさみ、そして再びもとの文に戻って続ける」という趣旨の説明がされています。
ですので、この「折挿法」は、「挿入句」か、もしくはそれに近いレトリックと位置づけることができます。

- 挿入句
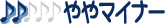
- 折挿法