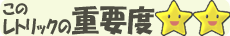サイト全部のトップ
サイト全部のトップ伏線 ふくせん preliminary
![『生徒会の一存』[上]2巻53ページ・[下]4巻41・42ページ([原作]葵せきな・[作画]10mo/富士見書房 DRAGONCOMICS AGE)](http://www.fukirhetoric.com/image/jpg/seitokaino2-53and4-41to42.jpg)
- 【(上)——episode 8】
- 鍵「ん――俺
- 中学の頃も帰宅部
- でしたからねぇ」
- 真冬「なんか意外です
- 凄く活動的な印象
- あるのに……」
- 鍵「あ――いや
- 中学の頃は単に
- 義妹(いもうと)がね……
- 真冬「義妹(いもうと)さんが?」
- 鍵「いや
- なんでもない」
- 真冬「今 さらっと
- 気になる伏線を
- 立てられた気がしましたが
- とりあえずいいです」
- 【(下)——episode.20】
- 鍵「ある時 俺は幼馴染みの
- 飛鳥から告白されたんだ
- 俺も彼女の事好きだったら
- 当然のように付き合う
- ことになった」
- 「だけど 妹はそれが
- 許せなくて
- ちょっと事件が起きて
- しまったんだよ」
- くりむ「事件?」
- 鍵「詳しい話は
- 勘弁してください」
- 「とにかく色々ありまして
- 妹は精神的に不安定に
- なってしまいまして……」
- 「入院生活を
- 余儀なくされるほどに ね」
- 妹もすごく
- 大事だったから……
- それから俺は
- 林檎に付きっきりの
- 看病生活を
- するようになった」
- ――以下続くけれど省略
伏線は、あとのほうでおこる出来事のマエフリをおくレトリックです。うしろにつづく話の展開を補強することになるような情報を、前のほうであらかじめ用意しておいておくことになります。
 「伏線」がどのように働くか考えることで、謎解きの気分を味わう
「伏線」がどのように働くか考えることで、謎解きの気分を味わう
- 受け手(聞き手・読み手)としては、思いがけないできごとが「伏線」だったと気がつくことになります。そしてそのことで、〈謎解きの快感〉を味わうことができます。これは、とくに推理小説では重要なポイントになります。
 :謎解き、謎、問い、関心、興味、求知心
:謎解き、謎、問い、関心、興味、求知心
 ストーリーを盛り上げて、ラストシーンで最高潮に達するようにする
ストーリーを盛り上げて、ラストシーンで最高潮に達するようにする
- 話を盛り上げるためには、非常に重要な手段となります。「伏線」を張らないでストーリーを進めると、ストーリーの最後で感じる〈謎解きの快感〉を味わうことができなくなってしまうのです。
 :盛り上げる、盛り上がる、高まる、高める
:盛り上げる、盛り上がる、高まる、高める
 ほのかにではあるが、確実に印象づけることが必要
ほのかにではあるが、確実に印象づけることが必要
- 「伏線」だと気がつかれては、失敗。さいごまで「伏線」だと思われなかったら、これも唐突になってしまうので失敗。ですので、ほのかに印象づけるくらいが、いちばん適しています。受け手(聞き手・読み手)が記憶の中に留めている程度の「伏線」が、望ましいといえます。
 :唐突、急に、出し抜け、突然、突如、不意、不意打ち、ほのか、ほんのり、ぼんやり、淡い、模糊、もうろう、不鮮明、かすか、うすうす
:唐突、急に、出し抜け、突然、突如、不意、不意打ち、ほのか、ほんのり、ぼんやり、淡い、模糊、もうろう、不鮮明、かすか、うすうす
 最後まで読んだ本を、また読み返すくらいの気分にさせる
最後まで読んだ本を、また読み返すくらいの気分にさせる
- 最後まで読んだ本を、また読み返す。すると、「ここが「伏線」だったのか」と気づくような「伏線」。このような時に、いちばん「伏線」が「伏線」として働きます。
 あとから出てくる情報を補強するできごと、それとなくばらまいておく
あとから出てくる情報を補強するできごと、それとなくばらまいておく
- あとから来るエピソードの布石になるような情報を、それとなくばらまいておく。すると、あとから起こるできごとを、正当化するような補強する材料になわけです。ただしあくまで、「それとなく」出されたものでなければなりません。
 :布石、用意、準備、手配り、手回し、手当て、補強、増強、それとなく、暗に、こっそり、こそこそ、そっと、さりげなく、なにげない、自然、おのずから、おのずと、何となく、まにまに、暗示、ほのめかす、におわせる、示唆、黙示、前ぶれ、きざし、知らせ、告げる、ぼかす、ぼやかす
:布石、用意、準備、手配り、手回し、手当て、補強、増強、それとなく、暗に、こっそり、こそこそ、そっと、さりげなく、なにげない、自然、おのずから、おのずと、何となく、まにまに、暗示、ほのめかす、におわせる、示唆、黙示、前ぶれ、きざし、知らせ、告げる、ぼかす、ぼやかす
 受け手が、すぐ気がつくようなものであっはならない
受け手が、すぐ気がつくようなものであっはならない
- あたりまえのことですが、「伏線」となるエピソードが「伏線」であると受け手(聞き手・読み手)が気づかれたら失敗です。これを避けるためには、巧妙な「伏線」を張らなければなりません。
 :巧妙、上手、うまい、器用
:巧妙、上手、うまい、器用
 「伏線」となる部分で、リズムを壊してはならない
「伏線」となる部分で、リズムを壊してはならない
- 「伏線」を張るために、あまりに細々としたエピソードをつくる。それは、受け手(聞き手・読み手)に「伏線」だと気がつかれなくても、長ったらしく、またリズムを壊すようなものになってしまいます。ですので「伏線」は、失敗する危険が大きいのも事実です。したがって「伏線」はふつう、短いパラグラフで行われます。
 :長ったらしい、長々と、長い、ロング、くだくだしい、くどくどしい、持って回った、回りくどい、遠回し、くだくだしい、くだくだ、たらたら、冗長、冗漫
:長ったらしい、長々と、長い、ロング、くだくだしい、くどくどしい、持って回った、回りくどい、遠回し、くだくだしい、くだくだ、たらたら、冗長、冗漫
 あまりに複雑な「伏線」をはってはいけない
あまりに複雑な「伏線」をはってはいけない
- 「伏線」が、いくつも張られる。すると、受け手(聞き手・読み手)としては、そのうちでどの筋がメインなのかが分からなくなってしまいます。ですので「伏線」は、あまり多くしてはいけません。
 :複雑、繁雑、煩雑、わずらわしい、煩瑣、ややこしい、面倒、手数、手がこむ、あざとい、小利口
:複雑、繁雑、煩雑、わずらわしい、煩瑣、ややこしい、面倒、手数、手がこむ、あざとい、小利口
 「伏線」には必ず、それと結びつく結果が求められる
「伏線」には必ず、それと結びつく結果が求められる
- 「伏線」に対応する「結末」がない。または、ある「結末」に呼応する「伏線」がない。そんな中途半端な作品は、許されません。
 :対応、相照らす、対照、対置、対峙、応じる、呼応、照応
:対応、相照らす、対照、対置、対峙、応じる、呼応、照応
- 例文は『生徒会の一存』。引用したイラストのうち、上の部分が2巻。下の部分が4巻からのものです。
このサイトで、この例を引用した理由。それは、伏線を立てられたと、登場キャラクター(真冬)自身が話しているからです。明らかに「伏線を立てられた」と書かれているのだから、伏線に違いない。であれば、この例を使うのが安全策といえるでしょう。
引用した部分を、くわしく見てみることにしましょう。
まず、引用した前半の部分(episode 8)では、と、鍵は義妹(いもうと)のことを言いかける。しかし、- 中学の頃は単に
- 義妹(いもうと)がね……
なんて言って、ことばを濁す。濁したことによって、棚上げの状態になってしまうわけです。- いや
- なんでもない
そして、中断して棚上げになったことが、後で明らかになる。それが、後半の部分(episode.20)というわけです。
つまり、というのが、「伏線」を使うことによって隠されていた事実だというわけです。- 看病生活を
- するようになった

- 伏線
 『シナリオ作法四十八章』(舟橋和郎/映人社)
『シナリオ作法四十八章』(舟橋和郎/映人社)
- 映画脚本のハウツー本です。映画の脚本でも「伏線」は重要なものになります。なので、かなりくわしい解説が書かれています。
 『プロの小説家になる作家養成塾』(若桜木虔/KKベストセラーズ)
『プロの小説家になる作家養成塾』(若桜木虔/KKベストセラーズ)
- こちらは、小説作家のハウツー本です。小説を書くときには、もちろん「伏線」が重要になります。
 「言いかけてやめる」というレトリック技法
「言いかけてやめる」というレトリック技法
- 鍵は、と、鍵は義妹(いもうと)のことを言いかける。しかし、
- 中学の頃は単に
- 義妹(いもうと)がね……
なんて言って、ことばを濁します。つまり、言いかけたままなのです。- いや
- なんでもない
こういったものは、「 中断法」といいます。