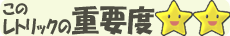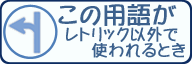- リリ「ここの言葉で
- オンガクとは
- 音を楽しむと
- 書くのだろう?
- その通りなのだ
- 音楽は誰にでも
- 楽しめるもので
- コンクールだって
- 音楽科だけの
- ものではない
- それをわかって
- もらいたい…
- もっと身近に
- 音楽を感じて
- 欲しいのだ!」
-『金色のコルダ』1巻75ページ(呉由姫・コーエー/白泉社 花とゆめCOMICS)転注は、同じような意味を持つ別のことばに、同じの字をあてることをいいます。「六書」の1つです。この「転注」については、まだ決まった考えかたはありません。ですが日本では、上に書いたような考えかたをとるのが一般的なようです。
 関連性のある意味を持ったことばを用意する
関連性のある意味を持ったことばを用意する
- 「転注」ではまず始めに、似たような意味を持った2つのことばを用意します。ここでは便宜上、もとになる「A」の意味を持った漢字を「甲」、それに似たことばは「B」という意味を持つものととしておきます。(なお、「B」をあらわす「漢字」はないものと考えるのが自然です。)
 :意味上の関連、関わりあいのある、関する、意味の類似、似る、似かよう、類同、相似、近似
:意味上の関連、関わりあいのある、関する、意味の類似、似る、似かよう、類同、相似、近似
 その、似たようなものことばに対して、おなじ漢字を当てる
その、似たようなものことばに対して、おなじ漢字を当てる
- ここで、「転注」がおこるとすると。
ここにはまだ、「B」に当てはまる漢字がない。じゃあ、似たような意味を持った単語から漢字を借りてきて使おう。「B」に似た意味を持ったことばは、「A」だ。そして、「A」が使っている漢字は「甲」だ。このようなことから、「B」を意味する漢字として「甲」が使われ始めます。これが、「転注」です。
 :転用、意味を転じる、意味を引きのばす、広げる、解釈の発展
:転用、意味を転じる、意味を引きのばす、広げる、解釈の発展
 転注は生まれたときから、ことばの原則に違反している
転注は生まれたときから、ことばの原則に違反している
- ことばの原則の1つに、「ことばの役割は、1つのことを伝えることにある」というものがあります。いいかえれば、1つのことばが2とおり、3とおりのことを伝えたりすると分かりづらいということです。この「転注」は、まさにこの原則の逆をしていることになります。ですので、やたらと「転注」を生みだされることはありません。
- このページのはじめの引用は、『金色のコルダ』1巻からです。
主人公は、日野香穂子。とある高校の普通科に通う2年生。
そして彼女が通う学校には普通科のほかに、音楽科が併設されていた。
でもまあ、たしかに音楽科が併設されているけれども、香穂子にはそれほど関わりもなかった。校舎も離れているし、接点がなかったから。
が、ある日香穂子は、決定的な出会いをしてしまう。その名前は「リリ」、音楽の妖精だという。
そして、その音楽の妖精リリは、大事な話があるといって、語り始める。
リリが見えるということは、何かしらの音楽的な可能性を秘めているハズ。だから、ぜひとも香穂子に、音楽科のコンクールに参加して欲しい。とかいって、リリは香穂子を説得していきます。
そして、そういったことを説得しているのが、いちばん上に引用のシーンです。
ここで、「転注」との関係で大切なのは、- ここの言葉で
- オンガクとは
- 音を楽しむと
書く- …
- 音楽は誰にでも
- 楽しめるもので
- …
音楽の「楽」の字が、「音楽」と「楽しい」の2つの意味で使われていること。そして、この2つが「意味」の連想によって結びついているところ。
そういったあたりが、「転注」とかかわってくることになります。
「転注」のくわしい説明については、以下の「レトリックを深く知る」をご覧ください。
 「転注」の作られかた
「転注」の作られかた
- 「転注」の作られかた。これについてはさいしょのほうにも少し書きましたが、もっとくわしく見ていくことにしましょう。
 「転注」の作られかた 1:まず、
「転注」の作られかた 1:まず、
- まず、「転注」が使われるとき。そのときには、「意味が似た」2つのことばを用意することが必要になります。たとえば、
- 「音楽」を意味することば(「楽」の字をもっている)
- 「たのしい」の意味することば(もともとは、漢字を持っていなかった)
という2つのことばです。「音楽を聴く・奏でる」ことが「たのしい」ことから、この2つのことばは似ているものだといえます。
 転注の作られかた 2:つぎに、
転注の作られかた 2:つぎに、
- この時点では、「楽」の漢字が使われているのは、「音楽を聴いたり、演奏したりする」ときだけでした。「たのしい」ばあいについては、その漢字は使われていませんでした。
しかし、
ここで「転注」が発生します。
音楽を聴いたり奏でたりすることは、「たのしい」ことだといえます。そこで、「楽」の字を「たのしい」という場合にも使おうと考えたのです。かくして、「楽」は「たのしい」という意味も持つようになります。
 転注の作られかた 3:さいごに、
転注の作られかた 3:さいごに、
- ただ、
それでは、1つのカタチのことばを2つの意味で使うことになります。それは、ことばとして分かりにくいものになってしまいます。
そこで、たいていのばあい、「転注」では発音が変えられることになります。
つまり、「転注」をすることによって生まれたことばと、もとのことばで使われていた発音。この2つを、別の発音とするのです。
たとえば、音楽に関係するような場合の「楽」は、「ガク」と発音します(たとえば、「楽師」「楽曲」)。ですが、「たのしい」といったような「キモチ」に関係する場合には、「ラク」と発音します(例えば、「苦楽」「楽園」)
「転注」前からあったことばに対しては「ガク」。そして、「転注」によって生みだされたことばについては「ラク」。このように「転注」では発音を変えるのが普通です。
 「転注」をレトリック用語で書いてみると
「転注」をレトリック用語で書いてみると
- 「六書」とは、漢字の文字の作られ方や使用法を6種類に分類したものをいいます。
そして、このうちの1つが「転注」というのことになります(残りは、象形・指事・形声・会意・仮借)。
ですので、この「転注」という呼びかた。これは、西洋レトリックの用語ではありません。
では、
西洋レトリックでいえば、この「転注」は何に該当するでしょうか。
これは、「同字異語(homograph)」と考えることができると思います。つまり、書きかたが同じで意味が異なることばに同じ字を使う。そのことによって、新しくことばを生みだす。それが「転注=同字異語(homograph)」というわけです。
なお「同字異語(同綴異義homograph)」は、
「
同綴同音異義」と「同綴異音異義」のどちらかのみを指していることがあります。ですが「転注」は、その両方ともを意味しています。
もっとも、上の方で書いたように、「転注」が起こると原則として発音は異なったものが使われます。ですので、たいていのばあい「転注」では、レトリック用語でいう「同綴異音異義」が起こっているものだといえます。
 サイト全部のトップ
サイト全部のトップ
 関連性のある意味を持ったことばを用意する
関連性のある意味を持ったことばを用意する :意味上の関連、関わりあいのある、関する、意味の類似、似る、似かよう、類同、相似、近似
:意味上の関連、関わりあいのある、関する、意味の類似、似る、似かよう、類同、相似、近似 その、似たようなものことばに対して、おなじ漢字を当てる
その、似たようなものことばに対して、おなじ漢字を当てる :転用、意味を転じる、意味を引きのばす、広げる、解釈の発展
:転用、意味を転じる、意味を引きのばす、広げる、解釈の発展 転注は生まれたときから、ことばの原則に違反している
転注は生まれたときから、ことばの原則に違反している 「転注」の作られかた
「転注」の作られかた 「転注」の作られかた 1:まず、
「転注」の作られかた 1:まず、 転注の作られかた 2:つぎに、
転注の作られかた 2:つぎに、 転注の作られかた 3:さいごに、
転注の作られかた 3:さいごに、 「転注」をレトリック用語で書いてみると
「転注」をレトリック用語で書いてみると

 「転注」には、まだよくわからない部分もある
「転注」には、まだよくわからない部分もある 『文字論』(河野六郎/三省堂)
『文字論』(河野六郎/三省堂) 『みんなの漢字教室(PHP新書 248)』(下村昇/PHP研究所)
『みんなの漢字教室(PHP新書 248)』(下村昇/PHP研究所)