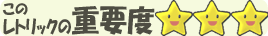サイト全部のトップ
サイト全部のトップ問答法・自問自答法 もんどうほう・じもんじとうほう dialogismus

- 院長(回想)(我々は人の命を救う以前に
- 学究の徒……そうだろ?)
- テンマ「!!そうじゃない!!
- 医者は人の命を救うのが第一だ!!
- エヴァ(回想)(人の命は
- 平等じゃないんだもの)
- テンマ「ちがう!!命に上下
- なんかあるもんか!!
- 僕は間違ってなんかいない!!」
問答法・自問自答法は、わざと対話の形式にするレトリックです。つまり、ふつうの文であっても表現できるのにもかかわらず、あえて「問いと答え」のかたちをとるものです。
 抽象的な話題に、ハッキリしたメージを与える
抽象的な話題に、ハッキリしたメージを与える
- 「問答法」は、表現力や説得力を高めるためのものといえます。言いかえれば、「考え」とか「意見」といった抽象的なものを論議するときに、抽象的になっているものを具体化することによって、イメージをはっきりさせるものです。
 :具体化、ハッキリ、くっきり、際やか、定か、ありあり、鮮明、明らか、明白、明瞭、瞭然、一目瞭然、見るからに、明白
:具体化、ハッキリ、くっきり、際やか、定か、ありあり、鮮明、明らか、明白、明瞭、瞭然、一目瞭然、見るからに、明白
 論点が、より明らかになる
論点が、より明らかになる
- 抽象的になってしまいそうな、議論のメインテーマ。それを「問答法」では、見落とすことなく、明らかにしておくという効果もあります。また、話のテーマが整理されるというメリットも、あります。
 :整理、ととのう、ととのえる、そろえる、そろう、まとまる、まとめる、整頓、片づく、片づける、テーマ、話題、議題、主題、論題、焦点、視点、着眼点、ピント、中心、核心、中核、中枢、枢軸
:整理、ととのう、ととのえる、そろえる、そろう、まとまる、まとめる、整頓、片づく、片づける、テーマ、話題、議題、主題、論題、焦点、視点、着眼点、ピント、中心、核心、中核、中枢、枢軸
 説得力や表現力を、高めることができる
説得力や表現力を、高めることができる
- あえて問いかけの方法をとる。そのことで、平叙文よりも説得力や表現力を高めることができます。
 :説得、説く、表現力、書きあらわす、言いあらわす
:説得、説く、表現力、書きあらわす、言いあらわす
 話題を共有し、連帯感をもたせる
話題を共有し、連帯感をもたせる
- 「問答法」のシーンを読んでいる(または聞いている)人。そういった人たちにとって、「問答法」は、議論となっている話題を共有させたり、連帯感を持たせたりする効果があります。
 :共有、連帯感、結ぶ、結びつく、結びつける、つながり、つながる、つなぐ
:共有、連帯感、結ぶ、結びつく、結びつける、つながり、つながる、つなぐ
 平叙文でも伝えることのできる文を、あえて問答形式にする
平叙文でも伝えることのできる文を、あえて問答形式にする
- 「問答法」は、あえて問答形式を取るというレトリックです。対話のカタチでなくても(つまり平叙文でも)伝えらえるもの。それをあえて、問答形式にするをとるのが「問答法」です。
 とくに「自問自答」のばあい
とくに「自問自答」のばあい
- 「自問自答」のばあいには、自分で出した「問い」にたいして自分で「答え」をするということになります。
- 引用は、『MONSTER』1巻から。
主人公は「テンマ」。
彼はドイツで脳外科医として仕事をしていて、その手腕は非常に優れたものだった。なので、院長に気に入られ、院長の娘である「エヴァ」と婚約をするまでになっていた。
しかしある日、たてつづけに2人の急患が病院にはこばれてくる。一人目は、男の子の子供。そして次に、市長が運ばれてきた。
「テンマ」は、最初に運ばれてきた男の子を手術する予定になっていた。しかしそこに、市長が急患として運ばれてきた。そして、院長は「テンマ」に、市長の手術をするように命令する。
だがしかし、「テンマ」は医療の原則を守って、早く運ばれてきた男の子の手術をした。つまり、院長の命令にしたがわなかった。結果、「テンマ」の執刀した男の子は助かる。しかし、市長のほうの手術は失敗し、市長は亡くなってしまう。
このように「テンマ」は、医者としての倫理観から行動をした。しかしそれが、院長の命令にしたがわないという事態を招いてしまった。結果、「テンマ」は院長の信頼を失って、「村八分」の状況におかれることとなる。
そんな中での自問自答が、引用の場面です。
院長や、その娘の「エヴァ」が言っているのは、- 「人の命を救う以前に 学究の徒」だ
- 「人の命は 平等じゃない」
といった、謀略的な言葉ばかり。それを思い返して、反論をしているのが引用のシーンです。
「問答法」は、このように心の中での自問自答だけを指していうものではありません。ですが、このようなものもパターンの1つとしてあげられます。
 「問答法」を適用する限界
「問答法」を適用する限界
- この「問答法」を、その適用される範囲を広いものと考えると、大変なことになります。つまり、相手と会話のやりとりをしているものを全て「問答法」ということにすると、大問題になります。
なぜなら、「ふき出し」はほとんどが「問答法」になってしまうからです。ふつう「ふき出し」は、話のやりとりで進むものです。つまり、登場人物が、おたがいに会話のキャッチボールをすることで成り立っているものです。それは、問答していることにほかなりません。とすれば、コミックスが「問答法」であふれている、と考える人が出てきかねません。
ですので、意識的に相手と意見を交換しているものに限って「問答法」と呼ぶことにします。
 「問答法」と「設疑法」との違い
「問答法」と「設疑法」との違い

- 問答法・問答・自問自答・自問自答