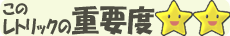サイト全部のトップ
サイト全部のトップ定義法 ていぎほう definition

- 和音「おまえ… 『神さま』って」
- なんだと思う…?」]
- 花鈴「…えっ… …えらい人?」
- (略)
- 和音「『5点』 民族や宗教によって
- 違うけど…… 強力なもの
- 慈悲深いもの 絶対的なもの
- 何かを つかさどるもの
- 何かを守るもの
- 花鈴「…守る…」
- 和音「いろいろあるけど
- だいたいこんな モンかな
- 花鈴… あのときおまえは
- 指輪を通じて
- 神の力を借りたんだ」
定義法は、ある事柄について短く説明するというレトリックです。つまり、ある物事の意味を明らかにするために、より詳しく端的に説明することを指します。
 ストーリーの多様性を生み、ことばに広がりを持たせる
ストーリーの多様性を生み、ことばに広がりを持たせる
- 「定義法」のポイント。それは、1つのコトバが持っている色々な意味の中で、そのうちの1点に集中させることです。1つのコトバは、たいてい2つ以上の意味をもっています。「定義法」では、その意味の中で1点に集中させることにあります。
 :多様性、多種、多様、多種多様、いろんな、とりどり、様々、種々、各種、各様、バラエティー、広がり、広がる、広げる、展開、拡大、拡張
:多様性、多種、多様、多種多様、いろんな、とりどり、様々、種々、各種、各様、バラエティー、広がり、広がる、広げる、展開、拡大、拡張
 議論で相手を反論するのに役立つ
議論で相手を反論するのに役立つ
- 議論で相手を反論するのに役立ちます。議論の相手が1つのコトバで攻撃してきたとき、それに対して、その(相手が使ってきた)コトバのうち1つの意味を使って反論する。すると議論の相手は、勢いをそがれてしまうことになるのです。
 :反論、言いあい、言いあう、言い争う、口論、論駁、反駁、抗議
:反論、言いあい、言いあう、言い争う、口論、論駁、反駁、抗議
 ある事柄について、重要なことを短く説明する
ある事柄について、重要なことを短く説明する
- 話の中に登場している人や物などを、手短に知らせたい。そんなときに使うのが「定義法」です。ですので「定義法」の「使い方」としては、いちばん重要だと思われる部分を手短に言うことが大切です。
 :重要、大事、大切、肝心、肝要、手短、簡約、ずばり、端的、直截、単刀直入
:重要、大事、大切、肝心、肝要、手短、簡約、ずばり、端的、直截、単刀直入
- 引用は、『かみちゃまかりん』1巻からです。
主人公は「かりん(花鈴)」という女の子。
「かりん」は両親を亡くしてしまい、さらにはペットのネコ(しーちゃん)まで死んでしまうという、不幸な境遇にいた。
そんな中で彼女は、お母さんの形見として「指輪」をつけていた。そして、その「指輪」には、なんと「神さま」になる力があるらしいということが分かってくる。
そこで「花鈴」が「和音」に対して、「神さま」とは何かということをたずねているシーン。「和音」は、「神さま」とは何かということを説明するために、「定義」というレトリックを使っているわけです。
この作品では、「神さま」の「定義」のうちで、「何かを守る」ということが、あとあと重要になっていきます。ストーリーでは「かりん」は「神さま」になったことによて、以上は「何かを守る神さま」という役割を果たすことになっていきます。
 「レトリックとは何か?」とかいうことではなくて
「レトリックとは何か?」とかいうことではなくて
- なんだか、レトリックの項目に「定義」というものがあると、「レトリックとは何か?」というようなことが書いてありそうです。つまり、「レトリックの定義」が書いてありそうな気がします。
ですが、ここで説明している「定義法」というのは、そういった「レトリックの定義」ではありません。あくまで、「定義」とか「定義法」とか呼ばれている、レトリックの分類のうちにある1つの項目です。
 「たんなる説明」とかいうことではなくて
「たんなる説明」とかいうことではなくて
- この「定義法」は、「成句」に関係するレトリックとも結びつくことがあります。たとえば、「ことわざ」とか「名言」とかいったものです。別の言いかたをすれば、「成句」(「ことわざ」「名言」など)の中には、「定義法」という方法をとっているものがあるということです。
たとえば。みたいなものです。こんなふうに、「○○とは、××である。」みたいなタイプになっている「ことわざ」「成句」には、「定義」というレトリックの要素も含まれていると見ることができます。- 「人間とは、考える葦である」(パスカル)

- 定義法・定義
 『レトリックの意味論—意味の弾性—(講談社学術文庫 1228)』(佐藤信夫/講談社)
『レトリックの意味論—意味の弾性—(講談社学術文庫 1228)』(佐藤信夫/講談社)
- 個人的に言えば、この本がいちばんオススメです。同じ者の『レトリック事典』(佐藤信夫[企画・構成])は事典という都合のため、平均的なことしか書いてありません。
 『レトリック辞典』(野内良三/国書刊行会)
『レトリック辞典』(野内良三/国書刊行会)
- こちらは、議論としての「定義法」が書かれています。「定義法」を意味するレトリックの項目の名前が、「定義‐議論」となっていることからも推測できます。