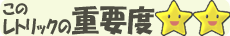サイト全部のトップ
サイト全部のトップ語中音添加 ごちゅうおんてんか epenthesis
![『生徒会の一存 にゃ☆』1巻22ページ([原作]葵せきな・[漫画]水島空彦/角川書店 角川コミックス・エース)](http://www.fukirhetoric.com/image/jpg/seitokaino.jpg)
- 司会「それでは生徒会長のお話です」
- 桜野くりむ(生徒会長)「み みなしゃん」
- 生徒一同(あ か
- かんじゃった)
- くりむ「みなしゃ…っ
- しゃ…さん
- ごきげんよう」
- 「気候もめっきり
- ポカポカと…
- 新緑が…ええと」
語中音添加は、単語の途中に音を差し込むというものです。
 発音をカンタンにすることができる
発音をカンタンにすることができる
- 語中音添加では、単語の中心に音を加えます。このことによって、発音がカンタンになります。多くのばあい語中音添加は、間違いやトリチガエの時に生ずるものなので、マイナス面にばかりを考えがちです。けれども、この語中音添加によって、発音が楽にできるようになるのは確かです。
 :(発音を)カンタンにする、容易に、なめらかに、スムーズ、手軽に、単純に
:(発音を)カンタンにする、容易に、なめらかに、スムーズ、手軽に、単純に
 詩に使われている効果を引き出す
詩に使われている効果を引き出す
- 詩の効果を高めるために、この「語中音添加」が使われることがあります。
 :詩的、詩
:詩的、詩
 新語を作り出す
新語を作り出す
- 単語の中心に音を加える。このことは、いままでの単語とはべつの意味の言葉をあらわすことになります。ですので、「語中音添加」によって作られた単語は、一種の新語ということが言えます。
 :新語、新造語法
:新語、新造語法
 子供っぽい登場人物が使っているような雰囲気が出る
子供っぽい登場人物が使っているような雰囲気が出る
- 子供はしばしば、「語中音添加」に分類されるような言い間違いをすることがあります。これは、子供のうちはまだ、言葉を話すのに使われる部分の発達が完成していないためです。そのため、「語中音添加」のような発音になってしまいがちということになるのです。このことから、「語中音添加」を使って話している人は、幼い子供であることも多くあります
 :幼い、いとけない、幼少、幼稚、子供、子供じみた、児童、幼児
:幼い、いとけない、幼少、幼稚、子供、子供じみた、児童、幼児
 音を単語の中に入れる
音を単語の中に入れる
- ここでは、「トンビ」という単語を例にします。この「トンビ」という単語は、もともと「トビ」だったはずです。しかし、早口ことばのように何度も使うと言いづらい。そこで「ン」の音を挟み込むことによって言いやすくする。これが、基本的な使い方です。
- 今回の画像は、『生徒会の一存 にゃ☆』から。
ここは、私立碧陽学園。そして、今まさに舞台へと歩いてきたのが、生徒会長の「桜野くりむ」。くりむは3年生だけど、ちっちゃい。でも生徒会長。
それは置いておいて。
くりむの「かんじゃった」のが、「語中音添加」ということができます。
正式な記号で説明するのがメンドウなので、ローマ字で説明させてもらいます。といったぐあいになります。ローマ字の「y」がつけ加えられています。- みなさん→
- minasann
- みなしゃん→
- minasyann
ですので、くりむのセリフは「語中音添加」だと言えます。
(まあ実は、音素の正式な記号で書いても、あまり大きな違いはないのだけれど)
 「語中音添加」に近いレトリック用語
「語中音添加」に近いレトリック用語
- このページであつかっているのは「語中音添加」です。この「語中音添加」には、仲間のようなレトリック用語が2つあります。それは、「語頭音添加」と「語尾音添加」の2つです。
つまり、単語の先頭に音が加えられると「語頭音添加」、単語の途中に音が加えられると「語中音添加」、そして単語の最後に音が加えられた場合には「語尾音添加」となります。

- 語中音添加

- 語中音付加・音中字挿入
 『現代言語学辞典』(田中春美[編集主幹]/成美堂)
『現代言語学辞典』(田中春美[編集主幹]/成美堂)
- 「語中音添加」についての説明文の長いもの。それを探してみると、この本だと思われます。(上の方で書いた)「トビ」→「トンビ」の説明も、この本に載っていたものです。