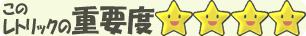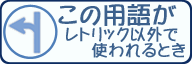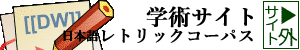サイト全部のトップ
サイト全部のトップ誇張法 こちょうほう hyperbole
![『まよチキ!』1巻46ページ(にぃと[作画]・あさのハジメ[原作]/メディアファクトリー MFコミックス アライブシリーズ)](http://www.fukirhetoric.com/image/jpg/mayochiki1-46.jpg)
- スバル「早く…
- 早くこの鎖を外してください!
- じゃないと そこの変態を
- 殺せません!」
- ジロー(…おかしいな
- 今、物騒な台詞が
- 聞こえた気が……)
- スバル「おい変態め!
- 殺してやる!殺してやるぞ!
- おまえの脳ミソを
- アルゼンチンまで
- ふっ飛ばしてやるからな
- ジロー(うわああ忘れてた!
- コイツは俺を 闇に葬ろうと
- してたんだっけ…!)
誇張法は、事実以上に大げさな表現をするレトリックです。つまり、ものごとの程度を高めて強調するものです。それは、自分の考えていることありのままに表現しようとして、極端なものとなってしまうものだといえます。
 伝えたいことを印象づける
伝えたいことを印象づける
- 伝えたいことを印象づけるために使われるのが、この「誇張法」です。
 :印象、焼きつける
:印象、焼きつける
 目の前で起きていることをうまく表現するために使われる
目の前で起きていることをうまく表現するために使われる
- ふつうの言葉では、目の前で起きていることを表現できない。そのばあいにも、「誇張法」は使われます。
 :目前、目の前、目のあたり、まん前、目先、間近、間近い、手近、至近、眼前
:目前、目の前、目のあたり、まん前、目先、間近、間近い、手近、至近、眼前
 ばあいによって、滑稽やユーモアを示すこともある
ばあいによって、滑稽やユーモアを示すこともある
- 必ず、というわけではありません。ですが時々、滑稽さやユーモア、面白さなどを出すことがあります。これは、ワザと「大げさ」な表現をとったことによる「おどけ」からから出てくる効果です。
 :詩歌、詩、和歌、短歌、俳句
:詩歌、詩、和歌、短歌、俳句
 調子を整えて余情を出し、味わいを生む
調子を整えて余情を出し、味わいを生む
- とくに詩などでは、コトバの位置を入れかえることがああります。これは、韻を踏んだり音の長さを整えたりするのに「倒置法」が役立つためです。
 :滑稽、面白い、おかしい、ユーモラス、ユーモア、面白い、コミカル、楽しい、愉快、快感、軽快、上機嫌、うれしい、ワクワク、興味津々
:滑稽、面白い、おかしい、ユーモラス、ユーモア、面白い、コミカル、楽しい、愉快、快感、軽快、上機嫌、うれしい、ワクワク、興味津々
 大げさに表現する
大げさに表現する
- 大げさに表現する大げさに表現するのが、「誇張法」の核心です。ただ、ここでいう「大げさ」というのは、「ウソ」とは違います。くわしくは
 を参照して下さい。
を参照して下さい。
 たんなる「ウソ」にはならないようにする
たんなる「ウソ」にはならないようにする
- 「誇張法」は、失敗するとタダの「ウソ」になってしまいます。そして「ウソつき」は、ふつう悪いものとして非難されます。くわしくは
 を参照して下さい。
を参照して下さい。
- このページの、さいしょの画像は、『まよチキ!』1巻から。
主人公は、ジロー。高校2年生の男。じつは、あまりフツーではない。けれども、そのあたりの事情は省略します。
これにたいしてヒロインは、スバル。同じく高校2年生。女。スバルは、執事をしている。そう、女の子なのに、それを隠して男として執事をつとめている。ここから、このお話が始まる。
ジローは、スバルがもっている秘密を知ってしまう。本当はスバルが「女である」ことをv知ってしまったのだ。
しかも、そのときのシチュエーションが最悪だった。スバルが女物のパンツをはいているのを、ジローが目撃してしまったのだ。そのためジローは、スバルに追われていた。ジローのことを「変態」だと、罵倒しながら。
そして、引用のシーンにたどり着きます。上に書いてきた事情で、スバルはジローのことを「変態」呼ばわりしています。その口からは、殺意がもれ出しています。
その殺意をあらわすセリフが、「誇張法」にあたります。たしかに、「殺してやる!」というのは不可能ではありません。ですが、「脳ミソをアルゼンチンまでふっ飛ばしてやる」というのは無理です。無理だと分かっていて、度を越えた表現をする。これが「誇張法」です。- スバル「おい変態め!
- 殺してやる!殺してやるぞ!
- おまえの脳ミソを
- アルゼンチンまで
- ふっ飛ばしてやるからな
「アルゼンチン」は、日本から見てちょうど地球の反対側にあたります。ですので、「遠い場所」の具体的な例として選ぶとすれば、理にかなっています。ですが、地球の裏側にあたるアルゼンチンに限らず、ふつうに考えて脳ミソをぶっ飛ばすことはできません。
そういったわけで、「誇張法」にあたるというわけです。

- 真悟「おれ、あんたには
- 裸見られても
- 平気かと 思ってた…」
- 遥「なわけないでしょ!?
- 相手の目、えぐっても
- 絶対見られたく
- ないわよ!!
- 真悟「わあっ!!」
主人公は「知立真悟」、15歳。
彼は、恐竜のような女に告白される。そして、恐竜のような裸のすがたを見せつけられる。そのため以後、重度の"女性恐怖症"となる。
その"女性恐怖症"を克服すべく、ボクシング部に入ることにする「真悟」。
しかしその行動は、早とちり。入部したのは、ボクシング部ではなく、「ボクササイズ部」だった。この「ボクササイズ部」というのは、「ボクシング」をとりいれた「エクササイズ」をしているという部活動。
そして、最初に書いた「恐竜のようなすがたをしていた、少女」が、「西春遥」という名前で、ボクササイズ部に入部していることを知る。
おどろいたことに彼女は、ボクササイズの効果によって「恐竜ようなすがた」から「美人」へと変身していた。
そこでの、ふたりの会話が、引用のシーン。
「真悟」は、元・恐竜女の「遥」のことを、「裸を見られても平気な女だ」と思っていたらしい。しかし、そんな女の人はいない。相手の目、えぐってものです。この部分が「誇張法」だと考えます。
絶対見られたくない
実際のところ、「相手の目をえぐる」のは、人間のできることではありません。「裸を見られるのが好きなわけでは決してない」ということを強調して、「相手の目をえぐっても、絶対見られたくない」と言っているわけです。
 「誇張法」に関係するレトリック
「誇張法」に関係するレトリック
 「誇張法」を2つに分類する
「誇張法」を2つに分類する
- この「誇張法」は、つぎの2つに分類されます。という2つです。
ただし。
世の中には「大きい」と「小さい」という尺度では、うまく表せないものもあります。
例えば「とてもからい」ということば。これは、「 過大誇張法」と「 過小誇張法」のどちらかに分類するには無理があります。
そのため、この「 過大誇張法」と「 過小誇張法」とは、原理的には同じものといえます。
もっといえば、すぐ上で引用したシーンの発言は「 過大誇張法」なのでしょうか。それとも、「 過小誇張法」なのでしょうか。
どちらかといえば、「 過大誇張法」のように思えます。ですが、「目をえぐる」ことが「大きい」ことなのかと言われると、ちょっと迷います。そういったわけで、引用した部分を「 過大誇張法」」だと断言することはできません。
このように、「 過大誇張法」と「 過小誇張法」のどちらなのか、分類に迷ってしまうものがあります。それも、わりと多く見かけます。
ですので実際には、「 過大誇張法」と「 過小誇張法」を分ける意味は、ほとんどないのです。
 「過小誇張法」と「緩叙法」との区別
「過小誇張法」と「緩叙法」との区別
- この「誇張法」は、「大げさに言って強調する」ことになります。ですが、これに対して「控えめに言うことによって、実際には強調することになる」というレトリックは、「
緩叙法(広義の)」と呼ばれます。
なのですが。
この点については、かなり難しい問題があります。それは、「 緩叙法(広義の)」と「 過小誇張法」の2つをどのように区別するかというところです。
この「緩叙法」と「過小誇張法」の区別については、古代のレトリック学者もかなり混乱していました。そして、いま現在のレトリック研究者たちもかなり混乱しています。そういったわけで、私(サイト作成者)も混乱しています。
なので残念ながら、今の段階ではハッキリとした区別のしかたを書くことはできません。
もう少し、頭の中がまとまってきたら、このサイトでも解説をしていきたいと思っています。
 そのほか「誇張法」に関係するレトリック
そのほか「誇張法」に関係するレトリック
- この「誇張法」と関連のあるレトリックとして、があります。くわしくは、それぞれの項目を参照して下さい。
 「ウソ」と「誇張法」との違い
「ウソ」と「誇張法」との違い
- 「誇張法」は、「ウソ」とは違います。
「ウソ」が「ウソ」であるためには、相手に「ウソ」だということを気がつかれれてはいけません。もしも気がつかれてしまったら、その「ウソ」は失敗だということになります。
それに対して「誇張法」は、ワザと大げさに言っているのだということが相手に分からなくてはなりません。現実にはそれほどではないんだけれども、極端な言いかたをすれば、それくらいの感じがした。とまあ、そういうことが相手に伝わってこそ、はじめて「誇張法」といえるのです。
たとえば。疲れて死にそうだ。ということばを聞いたとしても。だれも、この人を救急車に乗せて病院に運ぼうとはしません。それは、みんな誰しも、このことばが「誇張法」だということが分かるからです。どれだけ疲れているかを、大げさに言ってみた。極端なセリフにしてみた。そういった事情が、聞いている人に理解される。だから、「誇張法」という表現になることができるのです。
ただし、あまりに度を越して「誇張法」を使うと、読み手(聞き手)をシラけさせることにもなりかねません。それは、「誇張法」が現実をありのままに言っている表現ではない、ということから生まれてくる、あたりまえの注意点といえます。
 「誇張法」が使いづらい文章
「誇張法」が使いづらい文章
- この「誇張法」は、科学的な正確性を求められる文章には用いてはいけないレトリックだといえます。これもまた、「誇張法」が客観的な事実をそのまま伝えているわけではない、ということからくる、自然な考えです。
 「誇張法」によって表現する神仏の偉大さ
「誇張法」によって表現する神仏の偉大さ
- この「誇張法」は、宗教の世界では、古今東西を問わずに多く利用されています。
たとえば、聖書から一節を(これは『レトリック辞典』が挙げている例)。「イエスのなさったことは、このほかにもまだ数多くある。もしいちいち書きつづけるならば、世界もその書かれた文書を収めきれないであろうと思う。」(ヨハネによる福音書)といったふうに「誇張法」が用いられています。神仏の偉大であることを表現する際に、この「誇張法」はピッタリのレトリックなのです。
 定型化した「誇張法」
定型化した「誇張法」
- この「誇張法」には、「一日千秋」だとか「ノミの心臓」などのように、定式化した表現も多くあります。

- 誇張法・誇張

- 張喩

- 誇張表現

- 誇張的比喩・誇張語法・張喩法
 「倒裝法」を意味する「倒置法」
「倒裝法」を意味する「倒置法」
- まれに「倒置法」が、「倒装法」を意味するレトリック用語として使われることがあります。この2つは性質が似ているうえ、「倒装法」というレトリック用語がマイナーだからです。このサイトでは「hyperbaton,inversion」には「倒置法」をあてて、「hypallage」には「倒装法」をあてることにします。
 『日本語のレトリック—文章表現の技法—(岩波ジュニア新書 418)』(瀬戸賢一/岩波書店)
『日本語のレトリック—文章表現の技法—(岩波ジュニア新書 418)』(瀬戸賢一/岩波書店)
- 一見すると、子供向けの本に思われるかもしれません。ですが、取りあげているレトリック用語の説明は、かなりていねいです。「です・ます体」で書かれているので、人によっては合わないかもしれませんが。
 『レトリック感覚(講談社学術文庫 1029)』(佐藤信夫/講談社)
『レトリック感覚(講談社学術文庫 1029)』(佐藤信夫/講談社)
- 「誇張法」に、まるごと1つの章を使って解説してあります。やわらかい言葉づかいなので、レトリックの初心者でも読みこなせます。また、上級者・中級者でも十分読む価値のある本です。(というか、この本を読んだことのない上級者が、この日本にいるかどうかはアヤいしけれど。)
それと、『レトリックの記号論(講談社学術文庫 1098)』や『レトリックの意味論—意味の弾性—(講談社学術文庫 1228)』(佐藤信夫/講談社)にも、「誇張法」の解説があります。
 『レトリックの知—意味のアルケオロジーを求めて—』(瀬戸賢一/新曜社)
『レトリックの知—意味のアルケオロジーを求めて—』(瀬戸賢一/新曜社)
- おもに「誇張法」と「緩叙法」との違いについて書かれています。ですが上に書いたとおり、「過小誇張法」と「緩叙法」との分類は、学者の中でも一致していない点があるので注意が必要です。
 『レトリック辞典』(野内良三/国書刊行会)
『レトリック辞典』(野内良三/国書刊行会)
- 必要なことを、過不足なくまとめてある本です。同じ者の『レトリック入門—修辞と論証—』(野内良三/世界思想社)や『日本語修辞辞典』(野内良三/国書刊行会)も、あわせて参考になると思います。
 「ボクササイズ」について
「ボクササイズ」について
- 「ボクササイズ」ということばは、「ボクシング」と「エクササイズ」とをくっつけて作られています。なので、これは「
混成語・かばん語」にあたります。
この「 混成語・かばん語」については、そちらのページを参照してください。