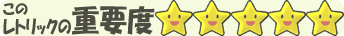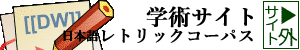サイト全部のトップ
サイト全部のトップ緩叙法(広義の) かんじょほう litotes

- 都筑「ゲームは何にいたしませう
- ドクター」
- 邑輝「ではポーカーで。
- ねえ都筑さん
- 私と勝負しませんか?
- チップではなく
- 何か別の物を賭けて…
- その方がスリルが あるでしょ?」
- 都筑「何を?」
- 邑輝「そうですね たとえば…
- 体とか。」
- 都筑「なに考えてんだ
- テメエはああ!!!」
- (なんてなんてなんて破廉恥なッ)
- 邑輝「たかがゲームじゃ
- ありませんか
- それとも私に負けるのが
- こわいんですか 都筑さん?」
- 都筑(うッ…
- い…嫌な予感が)
- あっ…の…
- もしも… 俺が負けたら?」
- 邑輝「決まってるでしょ?
- あーんなことや
- こーんなことや
- とても商業誌では
- 見せられないような
- 辱めをッッ!!
- (クックックッ
- ぜぇーんぶ試してあげましょうね
- 四十八手。)
- 都筑(やっぱりィ——っっ
- ぞくぞくぞくッ)
緩叙法(広義の)は、見せかけだけ、弱めた表現するレトリックです。
たしかに、表面上は「ひかえめ」なカタチをとっている。でも、それは見せかけだけのもの。本心は、大げさな表現よりかえって強調を狙っている。そういったレトリックです。
 露骨にいうよりも、意味深長
露骨にいうよりも、意味深長
- ものごとを露骨に言うのを避けることで、より深いメッセージを送ることができます。
 :露骨を避ける、暗に、それとなく、ひかえめ、乏しい、薄い、手薄、ひかえる、手控える、差し控える、意味深長
:露骨を避ける、暗に、それとなく、ひかえめ、乏しい、薄い、手薄、ひかえる、手控える、差し控える、意味深長
 遠回しに表現することで、皮肉・諧謔を盛りこむ
遠回しに表現することで、皮肉・諧謔を盛りこむ
- >遠回しに伝える、という「緩叙法」の特徴を利用する。そのことで、ふつうは言えないような皮肉や諧謔を表現することができます。
 :皮肉、皮肉る、あげ足、当てつけ、当てつける、アイロニー、諷する、諷刺、諧謔、おどけ、ユーモア、ジョーク
:皮肉、皮肉る、あげ足、当てつけ、当てつける、アイロニー、諷する、諷刺、諧謔、おどけ、ユーモア、ジョーク
 ものごとを遠回しに言うことで、つつしみ深く品格を保つ
ものごとを遠回しに言うことで、つつしみ深く品格を保つ
- 「緩叙法」では、ものごとを遠回しに言うことになります。そこから、つつしみ深く品格を保つようなフレーズを作ることができます
 :品格、品、気品、上品、つつしみ深い、つつしむ、自制、ひかえる、深長、用心深い
:品格、品、気品、上品、つつしみ深い、つつしむ、自制、ひかえる、深長、用心深い
 クールで冷静な感じをだす
クールで冷静な感じをだす
- 「緩叙法」を使うと、一歩離れたハタからの視線を持つことになります。そのため、ものごとに冷静・沈着な様子を表します。
 :クール、冷静さ、沈着、平静
:クール、冷静さ、沈着、平静
 ストレートに言わずに、間接的な表現をする
ストレートに言わずに、間接的な表現をする
- ストレートに言わずに、間接的な表現をする。「緩叙法」を使うばあいの、基本的な手法です。
 :間接、遠い、間接性、遠回し、婉曲、持って回った
:間接、遠い、間接性、遠回し、婉曲、持って回った
 見せかけだけ弱めることで、かえって強調する
見せかけだけ弱めることで、かえって強調する
- みせかけだけ弱めることで、単なる肯定よりもっと強調をすることができます。
 :みせかけ、うわべ、表面、おもてむき、外面、うわっつら、外見、外観、印象、焼きつける、インパクト
:みせかけ、うわべ、表面、おもてむき、外面、うわっつら、外見、外観、印象、焼きつける、インパクト
 あざとく利用されることがある
あざとく利用されることがある
- 「緩叙法」は、表面上のことばと真意とが正しくつながっていません。そこをついて、二枚舌のような言い回しを悪用するおそれがあります。
 :あざとい、さかしい、こざかしい、小利口
:あざとい、さかしい、こざかしい、小利口
 キザっぽい・イヤミな表現になりやすい
キザっぽい・イヤミな表現になりやすい
- 「緩叙法」を使いすぎると、キザっぽくなったり、イヤミになったりします。
 :キザっぽい、横柄、尊大、高慢、イヤミっぽい、いちゃもん、苦情、論難
:キザっぽい、横柄、尊大、高慢、イヤミっぽい、いちゃもん、苦情、論難
- 例文は『闇の末裔』3巻から。
主人公は、「都筑」。
「都筑」は、十王庁の中の閻魔庁で「死神」の仕事をしている。この世界では、死んだ人は十王庁へ送られることになっている。
しかし最近、香港で「死んだはずの人が十王庁に来ないで行方不明になる」という事態が起こっている。そこで、「死神」である都筑が原因究明のために動き出した。
どうも「華京院グループの豪華客船が怪しい」ということで、都筑はその客船に乗りこんだ。そこで、邑輝という男と再会する。その邑輝と都筑とのあいだの会話が引用のシーン(59〜60ページ)。長い引用になってしまいましたが、ポイントは、という部分。「あーんなこと」とか「こーんなこと」とか「とても商業誌では見せられないような辱め」とかが、具体的には何を意味しているのかは言ってはいません。ですが、この言葉がなにを意味するのかは、言うまでもないことです。まあ要するに、邑輝が都筑を狙っているわけです。- あーんなことや
- こーんなことや
- とても商業誌では
- 見せられないような
- 辱めをッッ!!
確かに、邑輝は具体的なことは言っていません。けれども遠回しに言うことによって、かえって強調の効果が出ています。ですのでこれは「緩叙法」に分類されます。
付け加えると。「言うまでもないこと」として言い逃れをするために、引用が長くなったともいえます。私(サイト作成者)は、「公然わいせつ」(刑法174条)や「わいせつ物頒布等」(刑法175条)で逮捕されたくはありません。ですので、作者にならって私も、具体的なことは書かないでおきます。
なお、細かい分類をしておけば、 「緩叙法」と「迂言法」「誇張法」との関係
「緩叙法」と「迂言法」「誇張法」との関係
- ほんとうのところ「緩叙法」の定義は、レトリック研究家によって一致していません。「 婉曲語法」やら「 過小誇張法」やらを巻きこんで、なにやら大論争になっております。
- そういった困った状況なのですが。このサイトでは、つぎのように定義しておきます。
- つまり、
という2つの性質を持っているものを、「緩叙法」としておきます。(手段) 迂言法の性質 : 遠回しに言うことになる ←遠回しに言わない「 過小誇張法」とは、違うもの (効果) 誇張法の性質 : 表現を強調することになる ←表現を強調しない「 婉曲語法」とは、違うもの
 「緩叙法」と「婉曲語法」との関係
「緩叙法」と「婉曲語法」との関係
- 「緩叙法」は、「
婉曲語法」と形の上では同じものになってしまいます。「緩叙法」と「
婉曲語法」はどちらも、表現それじたいは現実よりも「弱く」「小さく」示されているからです。
しかし、そのことばによって伝えようとしていることは、まったく逆です。「緩叙法」は、ほんとうは強調をねらったものです。しかし「 婉曲語法」は、ことばどおりに弱くすることを意図したものです。このように「緩叙法」と「 婉曲語法」は、送ろうとしているメッセージが正反対なのです。
ですので読み手(聞き手)は、それが「緩叙法」なのか、それとも「 婉曲語法」なのか、それをしっかりと見極める必要があります。
 「緩叙法(広義の)」の下位区分
「緩叙法(広義の)」の下位区分
- このサイトでは、「緩叙法(広義の)」を、次のように分類しました。この分類は、『レトリックの知—意味のアルケオロジーを求めて—』(瀬戸賢一/新曜社)によるものです。くわしくは、それぞれの項目を参照して下さい。
 「緩叙法」と「曲言法」との関係
「緩叙法」と「曲言法」との関係
- 「曲言法」は、「〜でない」のような否定的なことばを使って、強い肯定の意味を表すものをいいます。
ですので、上の にある「○否定を用いるもの」が、「曲言法」にあたります。
にある「○否定を用いるもの」が、「曲言法」にあたります。
けれどもこのサイトでは、すべて合わせて「緩叙法」として扱っておきます。これは個人的な考えではなく、「そのように説明している参考書が多い」という理由によります。
 「緩叙法」と「誇張法」との関係
「緩叙法」と「誇張法」との関係
- たぶん、『研究社英語学辞典』(市河三喜[編著]/研究社)がそのように書いているからなのでしょう。たいていの本には、「誇張法は緩叙法の反対」と書いてあります。
ですが、「誇張法は緩叙法の反対」というのは、その一面からしか見ていない。そのように私(サイト作成者)が思うのです。
下の図を見てみて下さい。
たしかに、「外見から見えるカタチ(形式)」の列では。「誇張法」が「強め」で「緩叙法」が「弱め」になっています。たしかに反対です。誇張法 ?? 緩叙法 婉曲法 目的 強め 弱め 強め 弱め 形式 強め 強め 弱め 弱め
けれども、「そのレトリックを使う目的(目的)」の列では、「誇張法」も「緩叙法」も両方とも「強め」になっているのです。反対ではありません。むしろ同じ効果が期待できるのです。
では、ほんとうに「緩叙法」の逆にあたるレトリック用語は何か?
探してみたけれども、思いつくものが見あたりませんでした。なので、そこの部分は「??」にしておきました。
 サイト作成者の「ひとりごと」
サイト作成者の「ひとりごと」
- ここから下は、サイト作成者としての「ひとりごと」。
引用したページで邑輝が言った言葉に、「体とか。」というものがあります。私が目を引かれたのは、その言葉の意味するところではありません。マンガのふき出しで「。」という句点が使われている点に、コミックスを読んだ当時には意外性を感じました。
ふつう、マンガのふき出しには「。」という句点を使われませんでした。松下容子先生は、たまにふき出しで「。」という句点を使うことがありますが、他の作者のマンガには、「。」という句点が使われることは滅多にありませんでした。
ただし原則的に、出版社が「小学館」のものに限っては、「、」「。」が使われていますけれども。
まあというわけで、マンガのふき出しで「。」が使われることは、すごく少なかったのです。
ですが。
今や、多くのコミックスで「。」(句点)を見かけるようになりました。こういったことを書くようになると、「私も歳をとったなあ」と実感するわけなのですが。
以上、サイト作成者の「ひとりごと」でした。