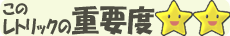サイト全部のトップ
サイト全部のトップ語頭音消失 ごとうおんしょうしつ aphaeresis, prosiopesis

- 警察官「こらーっ そこで
- 何やってるっ」
- -ここ1コマ省略します-
- ヤンクミ「サツだっっ」
- (ばっ)
- 「サツだっ わんわんだよ
- ちっくしょうっっ
- おいっサツだぞっ」
- 慎「わーかってるよ
- うるせ-っっ」
語頭音消失は、ことばの先頭部分を省略するレトリックです。つまり、語句の先頭に来るはずの音を、はぶことによってなくすものです。
 口語として使われはじめることが多い
口語として使われはじめることが多い
- 「語頭音消失」が、はじめに使われる。そんなシーンを2つに分けると、第1は、口語(話しことば)のシーンです。なるべく短い音で話をすませようとすると、自然と短縮していってしまうというわけです。
 :口語、話しことば
:口語、話しことば
 スラングから作られることも多い
スラングから作られることも多い
- 第2としては、スラング(俗語)から作られるばあいがあります。とくに「
隠語」のばあいには、この手のスラングが多く使われます。くわしくは、
 をご参照ください。
をご参照ください。
 :スラング、隠語、卑語、俗語
:スラング、隠語、卑語、俗語
 詩で韻律を整えるために使うことがある
詩で韻律を整えるために使うことがある
- たとえば、日本語の定型詩。多くのばあい音の数が7個とか5個に制限されます。短歌や俳句をイメージしてもらえば分かると思います。たしかに、字余りにしておくということもできます。ですが、それほど重要ではない音を取り去ってしまって、7個とか5個に合わせておくということもできます。
 :詩、詩歌、リズム、律動、リズミカル、律動的、韻律、歯切れ、語呂、調子、口調、語調
:詩、詩歌、リズム、律動、リズミカル、律動的、韻律、歯切れ、語呂、調子、口調、語調
 文や語の最初の音節を、削って使う
文や語の最初の音節を、削って使う
- 語(たまに語句、文)の最初の音節を削ったものを使うのが、「語頭音消失」です。このとき削られる音節は、多くのばあい1音です。ですがたまに、それ以上ということもあります。
- 引用は、『ごくせん』1巻から。
主人公は、山口久美子(通称:ヤンクミ)。
彼女は、すごい人。なんと、任侠集団の「黒田組」の四代目。そのヤンクミが新しく先生となり、高校に赴任することになる。しかしそこは、“絶滅寸前の「つっぱり高校生」が まだ のし歩いている”(10ページ)という、危ない学校。そこで、新人教師の教育の方法とかを校長先生たちが見学する、という「研究授業」が行われることとなる。
しかし、研究授業の当日。クラスの生徒全員が、屋上にエスケープ。そこで、教室に戻ってもらうというかわりに、慎という男子生徒とタイマンで勝負するハメにおちおいる、ヤンクミ。
で、その決闘場面が、引用のシーンです。サツだっっ
サツだっ
わんわんだよ
ちっくしょうっっ
おいっサツだぞっ
と、「サツ」というのが連発されています。説明するまでもなく、この「サツ」というのは「警察」の意味です。「ケイサツ」の「ケイ」が落っこちて、「サツ」になった。この部分が「語頭音消失」にあたります。
 「語頭音消失」と「短縮語」との関係
「語頭音消失」と「短縮語」との関係
- 「語頭音消失」は、「
短縮語」にふくまれるレトリックです。
「アルバイト」の「アル」が消えて「バイト」だけになったりするのが、この例にあたります。この「バイト」のように、「語頭音省略」をした「バイト」のほうが、もはや普段使うの形になりつつあるものもあります。
「語頭音消失」のほかに「 短縮語」にふくまれるものとしては、
があります。そちらもご参照ください。
このように、「 短縮語」には「語頭音消失」「 短縮語」「 語尾音消失」3つがあります。ですがその中で、一番よく使われるのは「 語尾音消失」です。
なぜかというと、言葉はその最初の部分に、その言葉全体を連想させるような情報を多く持っているからです。
 あえて「語尾音消失」を使うとき
あえて「語尾音消失」を使うとき
- 上に書いたように。ことばを短くするときには、「
語尾音消失」になることがが多いのです。それも、圧倒的といっていいほどの割合で「
語尾音消失」」になります。
それは逆にいうと、「語頭音消失」には、「語頭音消失」にしかないメリットがあるということです。つまり、「 語尾音消失」を使うのではでは差しさわりがあるばあいがあるということです。
ではその、「 語尾音消失」」を使いづらくなるような時とは何か。それは、「省略しようとしていることばが、あまり知られたくないもののようなばあい」です
それは、広い意味での「 隠語」を作ろうとしている、ともいうことができます。つまり、仲間うちだけにしか知られたくないような後ろめたい事情があるときとか。もしくは、もとのことばをダイレクトに使うとタブーになるときとか。あるいは、友だち関係などの集団どうしの結びつきを強めたいときとか。そういった、みんな誰しもに直接に知られると困るようなことばを短縮したいとき、「語頭音消失」になりやすいのです。
例文に出てきた、「警察→サツ」という「語頭音消失」のばあいも。そういった、広い意味での「[[[0040」といえます。まあ、「サツ」ということばは今や一般的になりすぎているので、あまり効果は期待できそうにありませんが。
 「語尾音消失」の長さ
「語尾音消失」の長さ
- ふつう。
ことばが省略されると、2音節から4音節くらいの長さにまとまります。ここでいう「音節」というのは、「ひらがな」「カタカナ」にしたばあいの文字の数と同じようなものだと考えてください(厳密には違うけど)。
ですので、「2音節から4音節くらいの長さにまとまる」といったばあい。おおざっぱにいえば、「省略することによって作られたことばを「ひらがな」「カタカナ」で数えると、2つから4つくらいになる」という意味になります。
それはなぜかというと。
省略したのにもかかわらず、まだこれ以上長いことばだとしたら。それでは省略した意味が、ほとんどなくなってしまいます。つまり「長すぎると、使いづらいまま」なのです。
だけど、もしもこれ以上短く省略してしまったとしたら。もはや何を言いたいのかが、分からなくなってしまいます。ようするに、「短すぎると、ことばとして伝わらない」のです。
だから、ふつう省略した言葉は2音節から4音節にまとまります。それはつまり、誤解をおそれずに書けば「ひらがな・カタカナの2文字から4文字に落ち着く」といったようなことです。

- 語頭音消失

- 頭部省略・語頭音消失・語頭音脱落
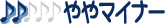
- 語頭音省略

- 冒頭省略・語頭削除・語頭音除去・上略
 『現代英語学辞典』(石橋幸太郎[編集代表]、勇康雄・宇賀治正朋・勝又永朗・鳥居次好・山川喜久男・渡辺藤一[編集]/成美堂)
『現代英語学辞典』(石橋幸太郎[編集代表]、勇康雄・宇賀治正朋・勝又永朗・鳥居次好・山川喜久男・渡辺藤一[編集]/成美堂)
- この「語頭音消失」をくわしく説明してある本には、いまのところ出会っていません。そういったわけなので、わりと平均的なこと語っている本として、これをあげておきます。